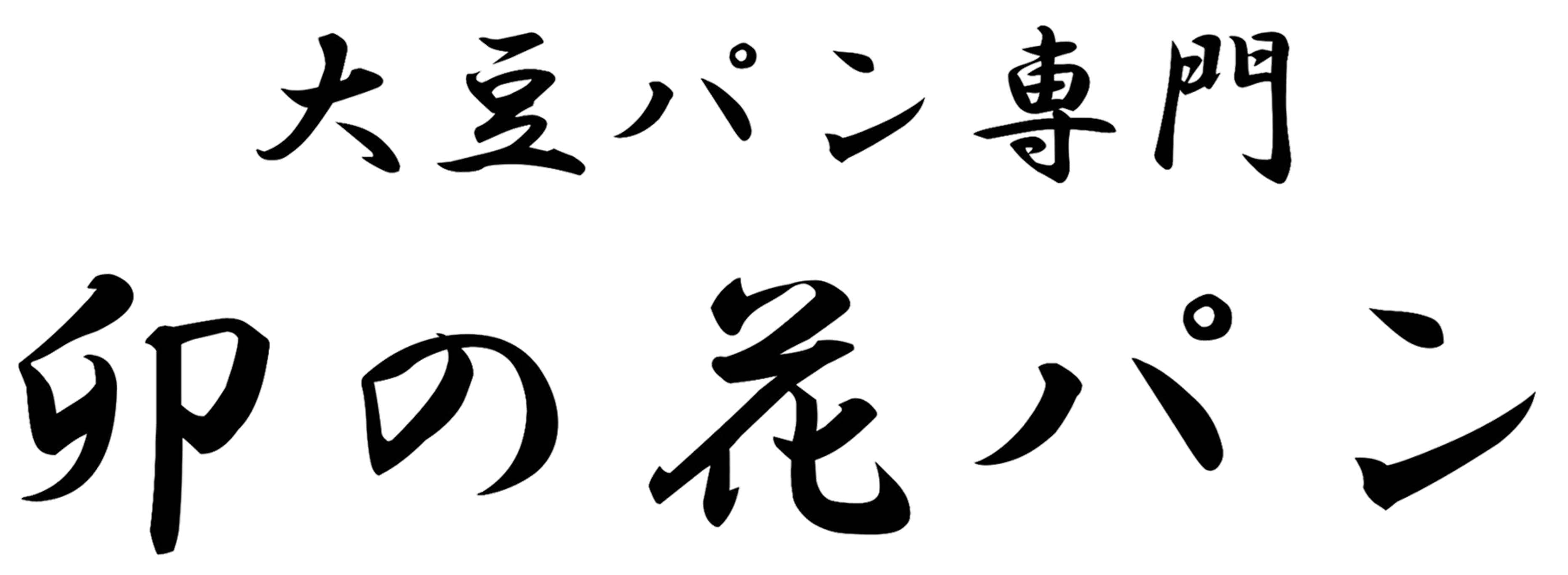大豆の実態をデータで解明
大豆君の大豆データ研究所
生産・消費・栄養データから見る大豆の今と未来
第1回 日本における大豆の需要と供給の現状
〇日本の大豆消費量の現状
日本における大豆の年間消費量は約300万トン(農林水産省「大豆の需給に関する資料(2023)」より)。これは決して少なくない量ですが、実は食用として消費されるのはそのうち**約25%のみで、残りの約75%は家畜の飼料用や工業用途(油脂製造など)**に使われています。
つまり、日本の大豆消費の大半は「直接食べるため」ではなく、「加工や畜産のため」に使われているのです。
👉 ポイント:「日本では大豆をよく食べているように見えるが、その多くは直接食べられていない!」
〇食用よりも飼料用が多い理由
なぜ日本では大豆の食用消費が少ないのでしょうか?
理由1:輸入大豆の大半が「搾油用」
日本は大豆の約94%を輸入に頼っている(農林水産省「大豆の需給に関する資料(2023)」)。
輸入大豆の大半は、食用ではなく油脂を搾るために使用され、その搾りかすが飼料に回される。
理由2:伝統的な大豆食文化の変化
昭和の時代には、大豆を使った味噌汁や煮豆が食卓に並ぶことが多かったが、近年はパンやパスタなど小麦中心の食生活が定着し、大豆の食用需要が減少。
若い世代ほど納豆・豆腐の消費が減少する傾向がある(総務省「家計調査(2022)」より)。
👉 ポイント:「輸入依存と食文化の変化が、大豆を食用よりも加工・飼料用途に向かわせている!」
〇世界と比較するとどうなる?
では、日本の大豆食用消費量は世界的に見て多いのでしょうか?
・日本人の大豆食用消費量:1人あたり年間約7kg(農林水産省)
・他国の消費量(食用のみ):中国:年間約14kg(日本の約2倍)、韓国:年間約10kg(日本の約1.4倍)
意外な事実:日本人は「大豆食文化」があるのに、実はあまり食べていない!
日本は豆腐・納豆・味噌など伝統的な大豆食品が多いが、それでも食用消費量は中国や韓国よりも少ない。逆に、中国では「豆乳」、韓国では「チゲ」など、大豆を積極的に食べる文化が根付いている。
👉 ポイント:「日本人は大豆をよく食べていると思われがちだが、実は世界基準で見ると少ない!」
〇今後の課題と行動指針
このデータから、日本の大豆消費には以下の課題があることがわかります。
課題1:食用大豆の消費拡大が必要
日本の大豆消費の大半は飼料用・加工用。
もっと食用大豆の利用を増やすべき!
課題2:食文化の変化への対応
若者世代の大豆食品離れが進行中。
大豆の新しい食べ方(パン・スイーツなど)を普及させることが重要。
行動指針:「大豆をもっと食卓に!」
食事の中に意識的に大豆を取り入れる(納豆・豆腐・豆乳・大豆パンなど)
家庭でも簡単に取り入れられるレシピを増やす
まとめ
✅ 日本の大豆消費量は約300万トンだが、食用は約25%しかない
✅ 日本の1人当たりの大豆食用消費量は中国や韓国よりも少ない
✅ もっと食用大豆を活用することで、健康的な食生活が実現できる!
参考データ(出典元)
農林水産省「大豆の需給に関する資料(2023)」
総務省「家計調査(2022)」
国際大豆協会「Global Soybean Market Report(2022)」
次回は…
▶ 「大豆の輸入量と国産大豆の現状」
「日本の大豆はどこから来ている?」をデータで解説!
お楽しみに!
----
大豆を美味しく食べるなら大豆パン!
大豆を食べよう 卯の花パン
----